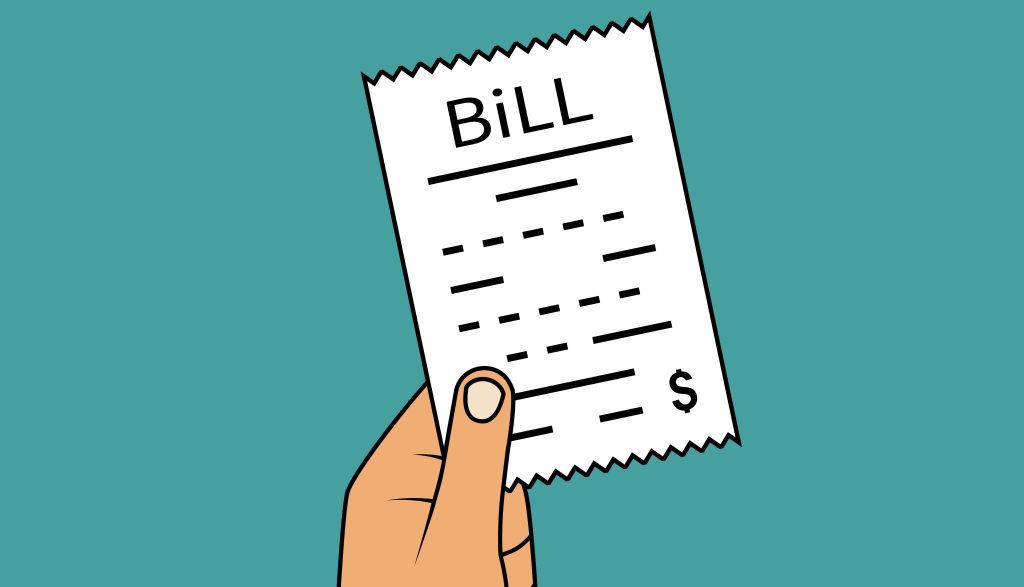法人税は、課税所得に対して一定の税率を乗じることで計算されます。
課税所得は、売上(益金)から経費(損金)を差し引いて計算されることから、損金が多く計上されると法人税額は低くなります。政府としては、無制限に損金が認められてしまうと税収入が低くなってしまうので、損金の計上の可否について一定の制限を設けています。
そこで、今日はUAE法人税法における損金について、日本の税制と比較しながら検討したいと思います。
法人税法上の損金の規定
損金とは、事業の遂行のために要した支出のことであり、課税所得の計算上控除されるものです。
支出は、それが発生した課税期間において控除が認められます。費用や支出がいつ発生するかは、その人の財務会計の基準によります(法人税法第 20 条)。
大まかに言えば、現金主義を採用する企業は支払時に支出が発生し、発生主義を採用する企業は、支払義務が発生した時(すなわち、支払のために取消不能な約束をした時)に支出が発生します。
法人税法第28条(控除対象支出)の項目において、企業の課税所得に対してどこまで損金を計上できるかについて規定しています。原則としては、事業目的のために行われた支出であり、個人の支払いと完全に区分されて発生した経費については原則としてすべて損金算入が認められています。
しかしながら、無制限に損金算入を認めてしまうと税収入の確保や企業間で不公平が生じるおそれがあることから、例外的に経費の計上に一定の制限を設けているものもあります。例えば以下のようなものが該当します。
接待交際費
事業または事業活動の一環として、例えば、既存または潜在的な顧客をもてなしたり、製品やサービスを宣伝したりするために費用が発生する可能性があることを法人税法上認めています。このような支出については、一般的な規定に従って、法人税法上の損金算入が認められるのが一般的です。
しかし、接待交際費は通常、ある程度の個人消費を伴うため、本来は事業用と個人用で支出を配分する必要があります。しかし管理事務の簡素化のために、課税対象者が事業用と個人用で支出を配分する必要なく、課税期間中に発生した一定の交際費の半分(50%)を控除することを認めています。
接待交際費は、得意先や株主、仕入先、その他のビジネスパートナーを接待する目的で使用するあらゆる支出に適用されます。
これには例えば以下のいずれかに関連する支出が含まれ、該当する交際費についてはその支出額の 50%のみを損金として控除することが出来ます(法法第32条1項2項)。
【接待交際費の例示】
- 飲食代
- 宿泊費
- タクシーや電車代などの交通費
- 入場料
- 娯楽、娯楽、レクリエーションに関連して使用される施設および設備の支出
ただし、従業員のために支出された接待交際費は、従業員が職務を遂行するために提供された場合、100%損金に算入されます。
【日本の交際費との比較】
日本の法人税法においても概ね同様の規定となっています。
ただし、会社の規模や単価によって取り扱いが異なります。・資本金または出資額が1億円以上の企業は、接待飲食費の50%が損金算入可能
・資本金または出資額が1億円未満の企業は、上記の50%基準以外に、年間800万円まで損金算入可能
・資本金の規模に関わらず、1件あたり5,000円以下の支出については会議費として計上可能
支払利息
純支払利子(支払利息のうち、同期間中に得られた受取利息を控除したもの)については、 EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益)の 30%までしか控除することが出来ません(法法第30条1項)。
しかし、発生時の会計期間で控除しきれなかった上記の純利息支出は10年間繰り越すことが出来、段階的に損金に算入することが出来ます(同条4項)。
ただし、関連当事者から融資を受ける際に発生した利息支出については、控除が認められません(法法第31条1項)。これには、配当や利益分配、課税対象者またはその関連者の資本構成の変更、出資、取得後に 関連者となる他の法人の株式取得などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
この規制は、関連当事者間で多額の支払利息を発生させることにより、不当に課税所得を圧縮することで法人税の課税ルールが損なわれないようにすることを目的としています。
そのため、金銭の貸付による利息の支払いを取引を行った主な目的が法人税の優遇を得るためで はないことを証明できる場合には、利息支出の控除制限は適用されません(同条2項)。
【日本の支払利息との比較】
日本においてもほぼ同様の税制(過大支払利子税制)がありますが、金額や期間などが異なります。日本の法人税法上、調整所得金額の「20%」を超える純支払利子については、その超える部分の金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入とし、翌事業年度以後「7年間」繰り越して一定の限度額まで損金算入を認めています。
その他
上記以外に支払った金額が損金として認められないものには、以下があります(法法第33条1項~9項)。
政策的な意図で損金算入を認めないもの
- 罰金の支払
- 寄付金(適格公益法人を除く)
- 賄賂やその他の不正な支払い
- 事業以外の費用、個人的な費用
1.3.罰金の支払いや賄賂については、違法行為を行うことによって(法人税の減額という形で)利益を受けることを防止し、罰金や罰則の抑止力を低下させないために、懲罰的な意味合いを持たせています。よって、このような支出について損金算入を認めていません。
2.寄付金(国が認めた団体以外)については、使い道が不明確になりやすく、支払者に資金が還流される可能性があることから、損金に算入できないこととされています。逆に、国の推奨する社会・公共福祉活動を奨励するため、適格公益 団体(Qualifying Public Benefit Entities)に対する寄付金、助成金、贈与に限って法人税の損金算入を認めています。
4.個人的な費用については、事業活動とは無関係であることから、当然に損金算入はできません。
損金という概念にそぐわないもの
- 非課税所得に関する支出
- 資本的支出に該当する支出
- 配当金の支払
- 回収可能なInput VAT
1.3.企業の所有者(株主)に行われる配当や利益処分、および類似の支払いまたは給付に対しては税引後の利益から行われるものであることから、税務上の損金とは認められません。
2.資本的支出は損金でなく資産として計上され将来にわたって損金に計上されるため、支出時に一括で損金になるわけではありません。
4.回収可能な仮払付加価値税(input VAT)、すなわち仕入時やサービスの役務提供を受けた際に支払ったVATに関しては、VAT申告の中で控除されることになるため、法人税法上の損金にはなりません。
損金として是認されるためにはどのような対策が必要か
上記で示したように、企業活動の範囲外や私的利用と認定された支出、内訳や使用用途が不明な支出に関しては、税務上損金として是認されない可能性があります。
企業は、発生した経費が事業に関連したものであることを証明するために、適切な書類を保持することを勧められます。適切に発行されたインボイスや領収書、その他発注書や見積書などの書類は捨てずに保管しておきましょう。
会計ソフトにPDFや画像データとして根拠資料を添付しておくことも重要です。
また、経費が事業活動と非事業活動に適切に分割されているかどうかを評価する必要があります。
今後は税務当局による税務調査が順次行われることも想定されます。過去にさかのぼって財務諸表を確認されることもあるので、過不足なく書類を整備できる体制を整えておくことが重要です。
まとめ
損金算入がどこまで認められるかということは、法人税の納税額に大きく影響します。
損金算入の可否やどこまで領収書等の書類を整備しておけば良いのかが不明な方や不安な方もいらっしゃると思いますので、お気軽に当会計事務所までお問い合わせいただければと思います。